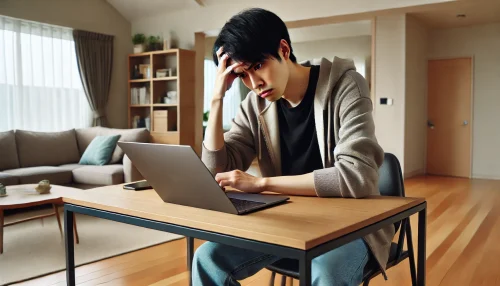
- 翻訳家が食えないと言われる理由が分かる
- 翻訳家の置かれる現状が分かる
- ChatGPTなどAIによって翻訳業界にどんな影響が出ているのかが分かる
- 翻訳家として食べていくために、今後どうしていくべきかが分かる
- これから翻訳家になる人が何を意識すべきかが分かる
翻訳家は食えない職業なの!?
最近はAIなどの進化によって、翻訳が人の手で行われることが少なくなってきています。
そのため、翻訳家という職業がクローズアップされにくくなっていることは事実です。
翻訳家は食えないという噂があるのは、どうしてなのしょうか?
主な5つの理由について、お伝えしていきます。
また、翻訳家として今後生き残っていくための戦略についても、ご紹介します。
今後のキャリアを真剣に考えるあなたにとって、きっと役立つヒントが見つかるでしょう!
翻訳家が食えないと言われる5つの理由とは?

翻訳家という仕事は、語学が好きな人にとって魅力的な職業です。
ですが、最近では「食えない」と悩む人が多いのも事実です。
どうしてなのでしょうか?
主な理由が次の5つ。
- 機械翻訳の精度が向上したから
- AIが凄い速度で進化しているから
- 収入が低い翻訳家が多いから
- 一部の優秀な翻訳家に仕事が集中するから
- 翻訳の仕事自体が減っているから
それぞれの理由について、見ていきましょう。
① 機械翻訳の精度が向上したから
翻訳家が食えないと言われる理由の一つが、機械翻訳の精度が格段に向上したことです。
特に「DeepL翻訳」や「Google翻訳」は、以前と比べて大きく進化しています。
昔は単語を並べただけのような直訳が目立ちました。
ですが、今では文脈を理解し、自然で読みやすい文章を生み出せるようになりました。
例えばビジネスメールや旅行先での簡単なやりとり程度であれば、機械翻訳でも十分に対応できてしまいます。
結果として、個人や企業が「翻訳家にお金を払う必要があるのか」と疑問を持ちやすくなりました。
費用削減を求める企業にとっては、無料で使える翻訳ツールの方が合理的なのです。
もちろん、全ての文章で機械翻訳が万能なわけではありません。
法律文書や医学論文のように専門性が高い文章、細やかなニュアンスが必要な場合などは、まだ人間の翻訳家が欠かせません。
ですが、世の中では「機械翻訳で十分」と判断されるケースが増えているのが現実です。
つまり、翻訳家がが必要とされる案件の数や種類が徐々に減ってきているのです。
このような背景から、多くの翻訳家が仕事を奪われやすくなり、「食えない」と言われる状況が加速しています。
② AIが凄い速度で進化しているから
翻訳家が食えないと言われる二つ目の理由は、 AIが凄い速度で進化していることです。
ChatGPTなどに代表されるAIは、単なる翻訳だけでなく、文章を整えたり要約も可能です。
場合によっては文脈に合わせて、新しい言い回しを考えたりすることもできます。
従来の翻訳家が担っていた翻訳+ライティングの領域をカバーする力を持っているのです。
例えば、企業が海外向けに商品説明を出すとき、以前なら翻訳家が訳した文章をライターが整える流れでした。
ところが今ではAIが一気に翻訳からリライトまで対応できるので、人件費も時間も大幅に削減できます。
そのため、費用重視の現場では非常に魅力的に映るため、翻訳家の仕事が減る原因になっています。
さらにAIは、進化が止まりません。
数か月ごとに新しい機能やモデルが登場し、その度に翻訳精度や文章生成力が格段に上がります。
利用者が多いと改善のサイクルも早く、翻訳家が追いつけないほどのスピードで進歩しているのです。
つまり、今「翻訳家の方が有利」と言われる領域も、数年後にはAIに取って代わられる可能性があります。
そのため、翻訳家は「AIにはできないこと」を探して自分の強みを築く必要があるのです。
③ 収入が低い翻訳家が多いから
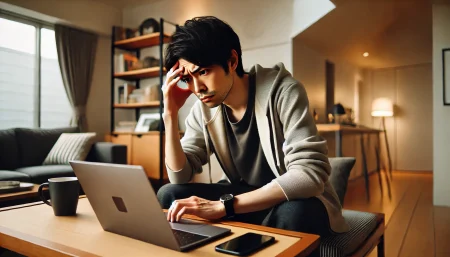
翻訳家が食えないと言われる大きな現実的な理由は、収入の低さもあります。
特にクラウドソーシングサイトを中心に活動する翻訳家は、1文字あたり1円以下という低単価案件に依存せざるを得ないケースが目立ちます。
仮に5,000文字を翻訳しても報酬が数千円にしかならず、時給に換算すると数百円程度になってしまいます。
これでは、翻訳家として生活をするのは、厳しいでしょう。
また、駆け出しの翻訳家は、実績を積むために安い案件を引き受けることになりがちです。
そのまま価格競争の渦に巻き込まれて抜け出せなくなるパターンが少なくありません。
一方で、翻訳業界には明確な報酬基準が存在しないため、顧客が提示した安価な価格が通りやすい傾向があります。
出費を減らすために、安く対応してくれる翻訳家に依頼が増えることになります。
そのため、安く引き受ける翻訳家が増えざるを得なくなり、「翻訳家は食えない」と感じやすい状況になっています。
④ 一部の優秀な翻訳家に仕事が集中するから
翻訳業界の特徴として、一部の優秀な翻訳家に仕事が集中することです。
企業や出版社は失敗を避けたいと考えるため、実績が豊富で信頼できる翻訳家に依頼する傾向があります。
その結果、新人や経験の浅い翻訳家には良い仕事はそうそう回ってきません。
こうして、業界内での格差が広がっているのです。
例えば、大手の翻訳会社や国際的なプロジェクトでは、数年来の取引実績を持つ翻訳家にしか依頼しないケースが多くあります。
品質保証の観点から当然の判断ですが、新規参入者にとっては大きな壁となります。
結果として、限られた上位層が安定して高収入を得ている一方で、その他大多数は低単価案件に頼らざるを得ません。
さらに顧客側も、「この翻訳家なら安心」と思える人物を選び続ける傾向があり、同じ人に案件が集中します。
そのため、実力があっても実績がない人は埋もれてしまいがちです。
翻訳家が稼げないのは単にスキル不足だけでなく、業界構造そのものにも原因があると言えます。
⑤ 翻訳の仕事自体が減っているから
最後の理由は、翻訳の仕事自体が減っていることです。
今は誰でもスマホやパソコンで翻訳アプリを使える時代です。
旅行や日常の会話、簡単なメールであれば、わざわざ翻訳家に頼む必要がなくなりました。
結果として、個人からの依頼が大きく減っているのです。
また、企業においても同じ現象が起きています。
費用削減の一環として、自社で機械翻訳を導入するケースが増えました。
特にウェブ記事やマーケティング資料のように、大量に発信されるコンテンツでは「スピードとコスト」が最優先されるので、機械翻訳の方が勝手がよいのです。
もちろん、専門分野では依然として翻訳家の需要があります。
法務や医学の分野では、誤訳が大きなリスクになるため、高いスキルを持つ翻訳家に依頼する価値があります。
とはいえ、一部の専門領域を除けば無料で十分という認識が社会に広がりつつあります。
このように、翻訳市場そのものが縮小している状況が「翻訳家は食えない」と言われる理由の一つになっているのです。
翻訳家が食えないと言われる状況で生き残るには?

先ほどのセクションでは翻訳家として食えない理由について、お伝えしてきました。
では、この状況を乗り越えるには、どうすればよいのでしょうか?
そこで、現在の翻訳業界の状況と、生き残るためのポイントについて、解説していきます。
まずは、翻訳業界の現状について、見ていきましょう。
翻訳業界の現状はどうなの?
翻訳業界の現状は、どうなのでしょうか?
結論から言うと、縮小傾向にあります。
翻訳業界が厳しい理由の一つは、先程の繰り返しになりますが、「AIの影響」が大きいです。
AI翻訳や生成AIが急速に普及しており、多くの人や企業が日常的に使うようになりました。
「わざわざ翻訳家に依頼しなくても済む」と考える人が増え、需要が減少しているのは事実です。
ただし、頭に入れておきたいのが全ての翻訳がAIに置き換わるわけではないという点です。
医療や法務など専門性が高く、正確さが最優先される分野では、人間にしかできない翻訳が求められます。
また、文化的な背景や微妙なニュアンスを反映させる必要がある文学作品や広告コピーなども同様です。
つまり、単純な文章はAIに任せればよいですが、高度な判断が必要な領域では翻訳家が活躍できる余地は残されています。
業界全体としては縮小傾向にあるものの、その中でどう生き残るかを考えていきましょう。
稼げるかどうかは自分の取り組み方に大きく左右される
翻訳家が食えないと言われる一方で、実際にしっかり収入を得ている人もいます。
この違いを生み出しているのは、自分の取り組み方で大きく左右されるためです。
同じ翻訳スキルを持っていても、安価な案件に偏っている人は低収入にとどまります。
各案件が低単価だと、数をこなしても、結果的に収益は伸びにくいです。
一方で、自分の強みを明確にし、直取引のクライアントを増やしている人は高収入につなげやすいです。
また、営業力や交渉力を鍛えることも重要です。
翻訳の質だけでなく、納期や対応力、提案力を含めた総合的な信頼を高めましょう。
顧客は値段以上に、品質や安心感を重視して選ぶ傾向にあります。
つまり、収入を決めるのは市場の状況だけではなく、自分自身の動き方も大事なのです。
高収入の鍵は専門分野の翻訳スキルを高めること
翻訳で安定して高収入を得るためには、専門分野の翻訳スキルを高めることが不可欠。
一般的な文章はAIや安価な翻訳者に置き換えられてしまいがちです。
しかし、専門性のある領域では話が違います。
医療、法律、IT、特許、金融など、専門知識が必要な分野は単価が高いです。
その上、対応できる人が限られるため、継続的な依頼につながりやすいのです。
例えば、医薬系の翻訳は誤訳が人命に関わる可能性があるため、報酬も高めに設定されています。
同じく法律文書は契約の有効性に直結するため、専門用語や文体を理解している翻訳家しか任せられません。
上記のような専門分野の翻訳スキルを確立すれば、他の翻訳者との差別化が明確になり、安定した収入を築けます。
つまり、専門分野を深掘りして強みを作ることが、「食えない」状況を乗り越える最大のポイントと言えます。
翻訳家に向いている人の特徴は?

翻訳家に向いている人には、どのような特徴があるのでしょうか?
主な特徴が次の3つ。
- 文章が好きであること
- 向上心があること
- 調べものが好きであること
翻訳は単に言葉を置き換える作業ではなく、文脈を理解し、自然な日本語として表現する力が必要です。
そのため、文章を書くことや読むことが好きな人が向いていると言えます。
また、向上心があることも重要です。
翻訳業界は常に変化しているため、学び続ける姿勢がないとすぐに時代遅れになってしまいます。
さらに、調べものが好きであることも大切です。
専門分野の翻訳では新しい用語や知識を調べる場面が多く、情報収集が必須だからです。
翻訳家に向いている人は、単なる語学力にとどまらず、知的好奇心や学習意欲を持ち続けられる人だと言えるでしょう。
通訳の選択肢も視野に入れてみよう
翻訳家だけにこだわらず、通訳という選択肢を視野に入れるのも有効です。
通訳はリアルタイムでの対応が必要になります。
特にビジネス会議や交渉の場では、相手の表情や空気感を読み取って言葉を選ぶ必要があり、人間ならではの強みがあります。
そのため、AIに完全に置き換えるのは難しいからです。
また、通訳経験は翻訳の仕事にもプラスになります。
現場で得た専門用語や表現の知識は翻訳業務に生かせるため、仕事の幅が広がります。
さらに、通訳と翻訳の両方をこなせることで、顧客からの信頼度も上がりやすくなるのです。
将来的なことも考えるなら、翻訳一本ではなく通訳スキルを組み合わせることも一つの有力な戦略と言えるでしょう。
翻訳家になるために把握すべきポイント

翻訳家を目指すなら、意識しておきたいのは現実を理解することです。
一見華やかに見える翻訳の仕事ですが、実際にはAIの普及や収入の低さといった課題が数多く存在します。
ですが、その厳しい現状を知った上で準備を進めれば、翻訳家としてのキャリアを築くことは十分に可能です。
最後のセクションでは、翻訳家を目指す人にとって重要な考え方や、未来につなげるためのポイントを整理して紹介していきますね。
翻訳家の将来性が厳しいことは事実
翻訳家の未来を考えるとき、多くの人が不安を抱くのはAIや機械翻訳の存在です。
実際にDeepLやGoogle翻訳は高い精度を誇り、一般的なビジネス文書や日常的なやり取りは人を介さなくても成立するようになってきました。
ChatGPTなどのAIも非常に早いスピードで進化しています。
その結果、翻訳の仕事全体は量的に減少し、特に経験の浅い翻訳家にとって案件獲得のハードルが高くなっています。
業界全体が直面している状況であり、食えないと噂が立つほど将来性が厳しいのは事実です。
ただし、全ての翻訳がAIや機械翻訳に奪われるわけではありません。
医療や法律、特許や学術論文などの専門分野では、正確さと深い知識が求められ、ミスが許されないため人間の翻訳家が不可欠です。
広告や文学といった感性や文化的背景を汲み取る分野も、機械には難しい領域です。
つまり「一般的な翻訳業務」の将来性は確かに厳しいものの、専門性を活かす翻訳にはまだ大きなチャンスが残されています。
翻訳家として活動を目指すのであれば、自分がどの分野で強みを発揮するのかを明確にする必要があるのです。
翻訳家になりたい理由を明確にしておくこと
翻訳家を目指す人にとって大切なのは、なぜ翻訳家になりたいのかを明確にしておくことです。
漠然と「語学が得意だから」「在宅で働きたいから」といった理由だけでは、現実の厳しさに直面した時に、心が折れてしまう可能性があります。
翻訳家になりたい理由が具体的で強いほど、困難な状況でもモチベーションを保つことにつながります。
例えば「医療翻訳を通して、日本の医療に貢献したい」「文学翻訳で海外の名作を日本に広めたい」などの思いがあれば、方向性が明確になります。
そのため、翻訳家を目指すなら、まずは自分の思いや考えを整理しましょう。
目指すべき目標がないと、翻訳家の厳しい現実に巻き込まれやすいです。
「なぜ翻訳家になりたいのか」を考えることは単なる気持ちの問題ではなく、キャリア形成にも大きく影響します。
将来迷ったときの軸にもなるため、翻訳家になりたい理由を明確にしておきましょう。
あなたならではの価値でプラスアルファを意識しよう
翻訳家として食えないと言われる状況を乗り越えるためには、あなたならではの価値を示す必要があります。
AI翻訳の精度が上がっている今、ただ原文を別の言語に置き換えるだけでは他の翻訳者との差別化ができません。
厳しい言い方になりますが、生き残ることができないのが現実です。
そこで重要になるのが、専門分野を深掘りすること・人間にしかできないニュアンスを表現する力をつけることです。
例えば、医療翻訳では最新の治療法や薬品名を理解するための専門知識が欠かせません。
広告翻訳では、直訳では伝わらない感覚的な魅力をどう伝えるかが重要になります。
文学翻訳では、文化的背景や読者の感情を意識して言葉を選ぶことが求められます。
こうした領域は単なる語学力だけでなく、人間の感性や知識が大きな武器になります。
翻訳家として長く活動するには、この「自分にしかできない付加価値」を意識し続けることが必要です。
依頼主からあなたにお願いしたいと思われる存在を目指していきましょう。
翻訳家が食えないと言われる5つの理由に関する総まとめ
翻訳家が食えないと言われる理由について、振り返っておきましょう。
- 翻訳家が食えないと言われるのは、機械翻訳の精度が向上したことが大きい
- AIが凄い早さで進歩しており、簡単に自分で翻訳をできる状況になってきている
- 翻訳家が食えないのは、低単価案件が多くなっている要因もある
- 一部の優秀な翻訳家に仕事が集中して稼げない人が多い
- 業界で生き残るためには、専門分野の翻訳スキルを高めることが鍵だ
- 将来性はAIに取って代わられる仕事が増える一方で、専門分野の需要はまだまだ見込める
- 翻訳家になるには、自分が向いている人かどうかを見極める必要がある
- 翻訳家に向いているのは、文章を書くのが好きで調べものに苦を感じない人だ
- フリーランスの翻訳は、仕事が安定しにくい
- 翻訳業界の将来性は厳しいが、医療や法律などAIに置き換えられにくい分野は残る
- 低単価に依存していると食えない状況に陥りやすい
- 営業力や交渉力も鍛える必要がある
- 通訳の選択肢を持つことも一つの選択肢
- 翻訳家が年収を上げるには、専門分野を掘り下げて差別化することが欠かせない
- 翻訳の仕事が来なくなったAI時代でも人間にしかできないニュアンス表現は強みになる
AIや機械翻訳の進化により、単純な翻訳の仕事が減ってきています。
そのため、翻訳家が食えないと言われる噂が強くなってきていることは事実です。
ですが、それはあくまで業界の一面であり、全ての翻訳家に当てはまるわけではありません。
実際には、専門分野に特化したり、自分ならではの強みを発揮することで安定した収入を得ている翻訳家も数多く存在します。
「翻訳家は食えない」という噂は、単純な翻訳業務が減っているという点では事実です。
しかし、専門分野を活かした翻訳には依然として大きな需要があり、誤解も含まれているのです。
重要なのは、その厳しい現実を正しく理解し、自分が生き残れる分野や方法を戦略的に選ぶことです。
将来を悲観するのではなく、自分の強みを活かして道を切り開く意識を持っていきましょう!






