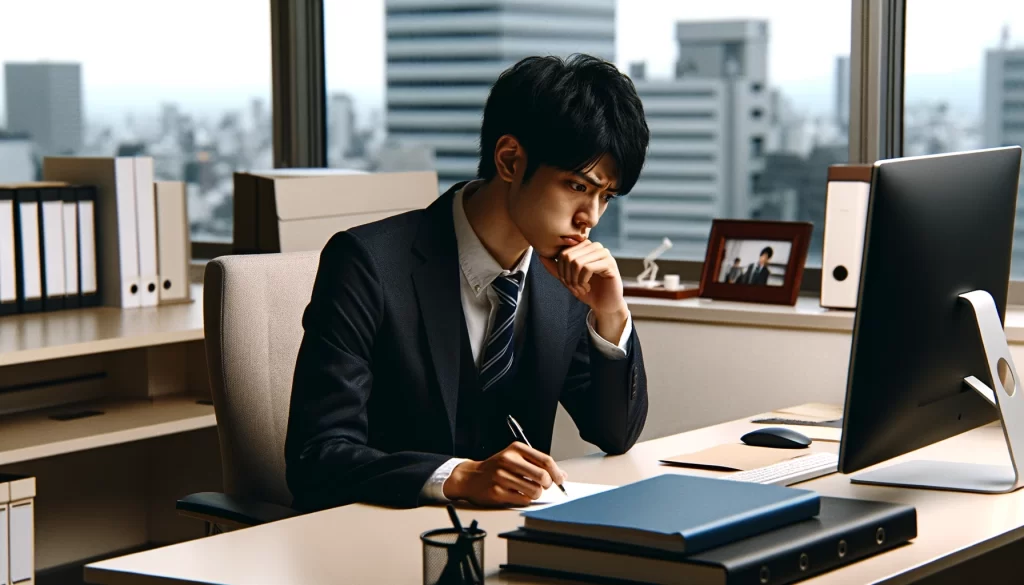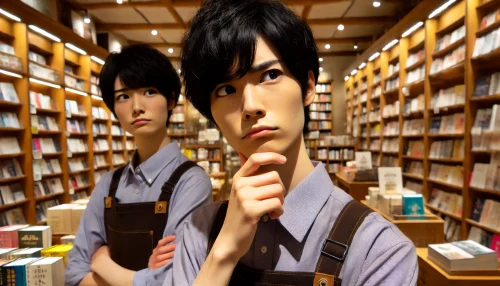
- 本屋の正社員がきついと言われる理由がわかる。
- 書店員の仕事内容の多さと体力仕事の大変さがわかる。
- 本屋の業界の仕組みがわかる。
- 書店員の将来性が不安視される理由と対策がわかる。
- 本屋の正社員になるために意識すべきポイントがわかる。
本屋の正社員がきつい?
そんな疑問を抱いて検索してきたあなた。
「書店員の年収」や「仕事内容」、「将来性」に不安を感じているかもしれません。
本屋の正社員がきついと言われるのはどうしてなのでしょうか?
主な7つの要因について、お伝えしていきます。
また、この状況を乗り越えるポイントについて、解説しますね!
「書店員になるにはどうすればいい?」「向いている人の特徴は?」
そんな疑問にも答えながら、“本屋で働くことの価値”を一緒に見ていきましょう!
本屋の正社員がきついと言われる7つの要因とは?

本屋の正社員がきついと言われるのは、なぜでしょうか?
主な7つの要因が下記です。
- 書店員で食べていけない人が増えてきたから
- 書店員の需要が少なくなってきているから
- 体力が必要だから
- 本屋の業界が薄利多売な仕組みだから
- 本のことは何でも知っていると思われやすいから
- 電子書籍・ネット通販が普及した影響が大きいから
- シフト勤務で連休を取ることが難しいから
それぞれの要因の詳細について、見ていきましょう。
① 書店員で食べていけない人が増えてきたから
本屋の正社員がきつい理由として多いのが、給料が安いという問題です。
これはもう、書店業界で働く上で避けて通れない現実です。
本屋の正社員の平均月収は、おおよそ18〜22万円前後。
地域や企業によって差はありますが、他の販売職やサービス業と比べても低めの水準です。
なぜ本屋の正社員は給料が安いのでしょうか?
それは、本1冊当たりの利益額が低く、収益が限られてしまうためです。
社員の給与を上げるためには、数百冊、場合によっては数千冊もの本を追加で売らなければなりません。
さらに、書店は固定費がかかります。
テナント料、光熱費、仕入れ、在庫などです。
「本が好き」という気持ちで働いている人も多いですが、生活のことを考えると続けるのが難しいと感じる人も一定数います。
② 書店員の需要が少なくなってきているから
次に挙げられるのが、書店員の需要が少なくなってきているという問題です。
全国の書店数は年々減っており、ピーク時の半分以下になったとも言われています。
原因はやはり、ネット通販や電子書籍の普及です。
本を買う場所が「書店」から「ネット」に移ったことで、リアル店舗の売上が落ち、採用枠も小さくなっています。
さらに、現在の書店は即戦力を求める傾向があります。
たとえば、棚づくりや発注業務の経験がある人、レジ操作やデータ分析に強い人などです。
ただし、需要がなくなったわけではありません。
むしろ、個性あるお店やブックカフェ型店舗、イベントを積極的に行う書店では、新しい力を求めています。
自分の得意分野を活かせる分野の書店を探すのがポイントです。
つまり、正社員になるチャンスは「減った」けれど、「消えた」わけではありません。
これからは、選ばれる店で選ばれる人になる努力が必要な時代であると言えるでしょう。
③ 体力が必要だから
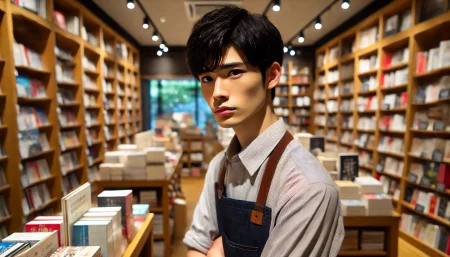
意外と知られていませんが、書店の仕事は体力が必要です。
「本屋=静かで穏やかな職場」と思っている人は、現場を見たらビックリするでしょう。
開店前は、新刊の段ボールが山のように届きます。
それを台車で運び、箱を開けて検品して、棚に並べていく。
本は紙のかたまりなので、一箱10kgを超えることもあります。
そして、営業時間中は基本的に立ちっぱなし。
お客様への案内、レジ対応、棚整理、在庫確認…。
閉店後も、売り場の入れ替えや返品処理などが続きます。
つまり、一日中動き回る仕事なんです。
そのため、腰痛や手首の腱鞘炎などに悩まされる人も少なくありません。
本屋の正社員は体力勝負というきつい側面も頭に入れておきましょう。
④ 本屋の業界が薄利多売な仕組みだから
本屋の正社員がきついと言われる精神的な要因が薄利多売の仕組みです。
一言でいうと、たくさん売っても利益がほとんど残らないのです。
例えば、1冊1,500円の本が売れたとします。
そのうちの大部分は出版社や取次(本の流通会社)に渡ります。
お店に残るのは、ざっくり2割くらい。
そこから人件費、家賃、光熱費、備品代などを引くと、本当にわずかしか利益が残らないというわけです。
そのため、どれだけ頑張っても給与が上がりにくい構造になっています。
本屋の業界が薄利多売な仕組みと言えます。
努力しても給与に反映されにくいため、将来的な希望が持ちにくく、精神的にきついと感じる人が多いのです。
⑤ 本のことは何でも知っていると思われやすいから
本屋の正社員をしていると、本のことは何でも知っていると思われやすいです。
例えば、下記のような質問。
- 昨日テレビで放映された小説の本はありますか?
- あの有名人が読んでたビジネス書はどれですか?
タイトルや著者が分からない質問をされるのは、まるでクイズのようです。
こういった質問が続くと、精神的にきついと感じる人もいます。
ですが、大切なのは知っていることではなく、一緒に探す姿勢です。
質問された時に「調べてみますね」と笑顔で答え、帯の特徴や話題になったメディアなどなどの情報を検索する。
上手な人は、こういう対応をしています。
とはいえ、本のことは知っていると思われやすいのがきつい部分ではあるでしょう。
⑥ 電子書籍・ネット通販が普及した影響が大きいから
最近本屋の環境を大きく変えたのが電子書籍とネット通販です。
両者の登場で、本屋の役割がガラッと変わりました。
昔は「本を買うなら本屋」しか選択肢がありませんでした。
でも今は、スマホから注文すれば翌日に届く。
また、電子書籍なら、買ってすぐに読める。
結果として、書店の数は減少し、「ただ本を売るだけ」では生き残れなくなりました。
本の買い方・読み方が大きく変わったのです。
本屋としては、きつい状況に陥っていることは間違いありません。
⑦ 土・日・祝の連休を取ることが難しいから
多くの本屋の正社員が「きつい」と感じる働き方が、休みの取りづらさです。
本屋は基本的にシフト制なので、土日や祝日に休みを取りにくいです。
つまり、連休を取ることが難しいということ。
土日や祝日は多くのお客さんが来店します。
週末は家族連れや学生、社会人など、休みの人が多いです。
どうしても人手が必要になり、土・日・祝の連休を取りにくくなるのです。
そのため、泊まりの旅行など週末の予定を組みにくい職種と言えるでしょう。
プライベートを重視する人には、きついと感じやすいです。
本屋の正社員がきつい状況を乗り越えるには?

先程は本屋の正社員がきついと言われる理由について、お伝えしてきました。
では、どのようにすれば、このきつい状況を乗り越えていけるのでしょうか?
次の3つに当てはまっていれば、乗り越えやすいと言えるでしょう。
- 本が好きであること
- 現代のスタイルに適応している書店を選ぶ
- 本屋の正社員に向いている要素がある
それぞれについて、見ていきましょう。
本が好きであること
「本が好き」という気持ちは、本屋の仕事を続ける上で一番のエネルギーになります。
この気持ちがあるかないかで、毎日の疲れ方も、仕事の楽しさも大きく違ってくるのです。
なぜなら、本屋の仕事は地味で細かい作業が多いからです。
本を並べて、検品して、返品して、フェアを準備して…。
派手なことは少ないですが、「この本を誰かに届けたい」と思える人は、そんな作業にもしっかりやりがいを見つけています。
本が好きな人は、自然と「新しい本」や「話題の作品」にアンテナが立ちます。
売り場作りや顧客対応につながり、評価されるキッカケにもなるのです。
本が好きであることはスタート地点であり、長く続けるための燃料とも言えるでしょう。
現代のスタイルに適応している書店を選ぶ
今の本屋業界は、昔ながらの「本だけを売る店」から大きく変化しています。
最近注目されているのは、ブックカフェや複合型店舗のように本+体験を提供するスタイルです。
代表例が、蔦屋書店やTSUTAYA BOOKSTOREなどの新しい形の書店です。
本を読むだけでなく、コーヒーを飲んだり、アートや音楽に触れたりする空間がつくられています。
お客様にとっては「本を買いに行く場所」ではなく、過ごしに行く場所になっているのです。
こうした店舗は、スタッフにも新しいスキルが求められます。
接客だけでなく、空間演出やSNS発信、イベント企画など、多方面の感性や発想力が活かせます。
言い換えれば、創造的な仕事がしたい人にとってチャンスの多い職場なのです。
本を通して人が集まり、時間を共有する。
そんな空間を自分の手で支えることができるのは、書店員という仕事ならではのやりがいです。
つまり、時代の変化を恐れないことが、きつい状況をチャンスに変える一歩と言えるでしょう。
本屋の正社員に向いている要素があること
自分が本屋の仕事に向いているかを考えてみましょう。
これを知っておくだけでも、本屋の正社員として働く上できついと感じる状況が全然違ってきます。
まずは、ある程度の体力仕事ができること。
書店では、重い本を運ぶ、本を並べる・整理する、長時間立ちっぱなしで接客するなど、体を使う場面が多いです。
そのため、体力には全然自信がないという方には、オススメができません。
そしてもう一つ大事なのが、人と関わることが好きであることです。
本屋はただの“モノを売る仕事”ではなく、“人と人をつなぐ仕事”です。
お客さんとの会話の中で本を紹介したり、悩みを聞いてピッタリの一冊を提案したりすることもあります。
そして何より大切なのが、繰り返しになりますが本が好きであること。
上記の要素を持っていれば、きついと感じることがあっても、きちんと乗り越えていけますよ!
本屋の正社員になりたい人が押さえておくべきポイント

昨今の書店業界は時代の変化によって、将来に不安を感じる人も多いです。
では、本屋で正社員として働く上で、どのようなことを意識すればよいのでしょうか?
最後のセクションでは、「これから本屋の正社員を目指す人」が押さえておくべきポイントをご紹介します。
現場でのギャップに戸惑うことなく、長く働くための土台を意識していきましょう。
書店員の将来性が厳しいことは頭に入れておこう
まず最初に、現実から目をそらさないことが大切です。
書店員の将来性が厳しいことは事実。
理由としては、全国の書店数が減少し続けていることにあります。
公益社団法人 全国出版協会のデータによれば、最近は店舗数は大幅に減っています。
ここ20年で書店の数は、約半減しています。
電子書籍やWebサイトが読書の主流になりつつあるため、リアル店舗の売上が厳しいのです。
だからといって「将来性がない=やる価値がない」というわけではありません。
今の書店員は、単なる販売員ではなく、本を通じて人をつなぐ役割を担っています。
例えば、地域密着型のイベントを企画したり、SNSで読書の楽しさを発信したりなどです。
デジタルが進む中でこそ、アナログな温かみが求められています。
つまり、「必要とされている仕事」なのです。
現実を理解した上で、どう価値を生み出せるかを考える人こそが、これからの書店員として輝くことができるでしょう。
正社員の募集は少ない
次に覚えておいてほしいのが、本屋の正社員採用は狭き門だということです。
大手チェーン書店でも、常に正社員を募集しているわけではありません。
多くの場合は、アルバイトや契約社員からの登用です。
なぜかというと、店舗の規模が限られているうえに、人の入れ替えが少ないからです。
一つの店舗に正社員が数名しかいないというケースも珍しくありません。
そのため、採用では「すぐに現場で動けるか」「コミュニケーション能力があるか」など、即戦力としての資質を重視されます。
単に「本が好きです」だけでは通用しづらいと言えます。
ただし、逆にいえば、経験を積めばチャンスはあります。
書店の現場では、アルバイトであっても棚づくりやイベント企画などを任せてもらえることがあります。
そうした経験を積んでおけば、正社員登用の話が出たときに有利になります。
実際、現役の正社員の中には「最初はアルバイトから始めた」という人も多いです。
焦らず、地道に現場で信頼を築いていけば、道は開けていきます。
チャンスを自分の努力でつかんでいきましょう。
これからの本屋の正社員は柔軟な発想が必要
今後、本屋の正社員として長く働いていくためには、柔軟な発想が欠かせません。
昔ながらのやり方に固執してしまうと、これからの時代には対応できなくなってしまうでしょう。
なぜなら、書店業界は今、これまでにないスピードで変化しているからです。
電子書籍、SNSでの本紹介、オンラインイベント、地域連携フェアなどなど。
10年前には想像もしなかったような流れが次々に出てきています。
こうした流れの中で求められるのは、「本を売る人」から「本の価値を伝える人」への変化です。
例えば、好きな作家の特集コーナーを自分で企画してSNSで発信する。
そんな発想ができる人は、お店の雰囲気をガラッと変える力を持っています。
これからの本屋の正社員は「売り場を守る人」ではなく、「未来をつくる人」になる必要があります。
変化を恐れず、自分の感性を武器にできる人が、これからの書店をリードしていくでしょう。
本屋の正社員がきついことに関する総まとめ
本屋の正社員がきつい理由について、振り返っておきましょう。
- 本屋の正社員がきついと言われる理由は、年収が低く生活が厳しい現実にある
- 書店員の仕事内容は地味だが膨大であり、在庫管理・接客・イベント企画まで求められる
- 本屋の正社員がきつい原因の一つは、薄利多売の構造にある
- 本屋の正社員きついのは、重い本の搬入や立ち作業など体力面の要因もある
- 電子書籍や通販の台頭で店舗数が減少していることで、書店員の将来性は不安視されている
- 書店員に向いてる人は、本を愛しつつ人とのコミュニケーションを楽しめるタイプである
- 本屋の正社員の求人は減少傾向にある
- シフト勤務で連休を取りにくい勤務体系が多い
- 書店員が年収を上げるには、発注・棚づくり・SNS発信などで売上に貢献することが必要だ
- 本屋の正社員は知識量を問われる
- 書店員に向いてる人の共通点は、「好き」を仕事に変えられる柔軟な発想を持っている点だ
- きつい状況を乗り越えるには、ブックカフェなどがある現代型の書店スタイルを選ぶこと
- 人と人をつなぐ仕事である意識が大切
- 「本が好き」という原点が本屋で働き続ける力になっている
ここまで読んでみて、「本屋の正社員ってきついイメージ…」と感じた人もいるかもしれません。
でも、それは半分は正解で、半分は間違いです。
確かに、本屋の仕事は体力も気力も使います。
給料が高いわけでもないし、休日が少ないこともある。
ですが、その大変さの中に人の心に本を届ける喜びがあります。
大切なのは、楽な仕事を探すことではなく、自分にとって意味のある仕事を見つけること。
本屋の正社員という仕事は、まさにその代表だと思います。
だからこそ、これから目指す人は、「好き」と「現実」の両方を理解した上で、一歩を踏み出してみましょう!